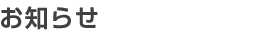<参加者募集は終了しました>
「恵みの宝庫“吉野川”創造プロジェクト」の一環として、吉野川との関わりによって育まれてきた歴史・文化・環境をテーマに、吉野川の魅力をお伝えする「まるごと吉野川魅力再発見講座」を開催します。
◎開催日
令和8年1月10日(土)12:00~16:55
◎内容
現場からみる吉野川~中鳥島・うだつの町並み歴史探索バスツアー~
◎対象・定員
20名程度(申込多数の場合は抽選)
(小学生以下は保護者同伴)
◎参加費 無料
◎申込〆切
令和7年12月19日(金)17時必着
◎申込方法
添付の「チラシ」の申込書または必要事項を記入し、次のいずれかの方法でお申し込みください。
1.メール kasenseisakuka@pref.tokushima.lg.jp
2.郵送 〒770-8570徳島市万代町1丁目1番地
徳島県庁 河川政策課 宛
※詳細はチラシでご覧ください。
2025年12月9日火曜日
2025年9月9日火曜日
吉野川流域の魅力をパネルで紹介します!令和7年度「吉野川魅力発見パネル展」
徳島県では、吉野川から得られる「恵み」を「にぎわい(観光・交流)」、「なりわい(産業振興)」、「かたらい(歴史・文化・環境)」の3つの視点で捉え、「川の魅力」を県内はもとより全国にPRする取組を通して、地域振興に役立てる「恵みの宝庫“吉野川”創造プロジェクト」に取り組んでいます。
この一環として、県内外の方々に、吉野川の魅力をお伝えするため、パネル展を開催いたします!
◎期 間 令和7年9月8日(月)から9月16日(火)まで
◎場 所 徳島県庁 1階 県庁ふれあいセンター
(徳島市万代町1丁目1番地)
◎内 容 川を通じたイベント活動への取組
◎主 催 吉野川交流推進会議、徳島県
この一環として、県内外の方々に、吉野川の魅力をお伝えするため、パネル展を開催いたします!
◎期 間 令和7年9月8日(月)から9月16日(火)まで
◎場 所 徳島県庁 1階 県庁ふれあいセンター
(徳島市万代町1丁目1番地)
◎内 容 川を通じたイベント活動への取組
◎主 催 吉野川交流推進会議、徳島県
2025年7月1日火曜日
「交流体験 in よしのがわ 2025」参加者募集について(終了)
<イベント・参加者募集は終了しました>
徳島県内小中学生とその保護者の方を対象に、吉野川の良さを実感してもらうとともに、川を通じた交流を深めるため、今年も「交流体験 in よしのがわ」を開催します。※詳細については、募集チラシをご覧ください。
※応募者多数の場合は、申込単位で抽選します。
■申込方法(上流編・中流編・下流編共通)
申込書に記入の上、次のいずれかの方法でお申し込みください。
□郵送の場合
〒770-8570 徳島市万代町1丁目1番地
徳島県庁 生活環境政策課内 「吉野川交流推進会議」宛
□メールの場合
seikatsukankyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp
※抽選結果はメールでお知らせしますので、メールを受信できるようにしてください。
※メール件名に「上流編or中流編or下流編」、本文に次の項目を記載してください。
本文への記載事項
1 代表者氏名
2 代表者携帯電話
3 代表者居住市町村名
4 参加者全員の氏名と年齢
・上流編に申込の方は、参加者全員の身長と体重
5 上流編(ウォータースポーツ)、中流編(カヌー)に申込の場合、
保護者の方が「体験に参加」or「見学」いずれかを記載してください。
■参加費 無料
■上流編 「水難事故防止講習&ウォータースポーツ体験!」
・開催日 2025年8月2日(土)受付12:00~(開始12:30~)
・集合場所 池田湖水際公園(詳細はPDF裏面参照)
・対象・定員 徳島県内の小中学生とその保護者20名程度
・主催 吉野川交流推進会議・国土交通省・徳島県
・申込締切 2025年7月23日(水)必着
・申込書・募集チラシ 2025年交流体験inよしのがわ(上流編)【PDF添付】
■中流編 「水難事故防止講習&カヌー体験」
・開催日 2025年7月23日(水)受付9:30~(開始10:00~)
・集合場所 AMEMBO事務局(美馬市美馬町中鳥地先)
・対象・定員 徳島県内の小中学生とその保護者30名程度
・主催 吉野川交流推進会議・国土交通省
・申込締切 2025年7月16日(水)必着
・申込書・募集チラシ 2025年交流体験inよしのがわ(中流編)【PDF添付】
■下流編 おさかな博士の川魚かんさつ&水難事故防止講習
・開催日 2025年8月4日(月)受付9:00~(開始9:30~)
・集合場所 鮎喰川・梁瀬橋(やなせばし)付近(徳島市入田町)
・対象・定員 徳島県内の小中学生とその保護者30名程度
・主催 吉野川交流推進会議・国土交通省
・申込締切 2025年7月24日(木)必着
・申込書・募集チラシ 2025年交流体験inよしのがわ(下流編)【PDF添付】
■天候不良等により、中止または開催内容を変更する場合があります。
2025年4月9日水曜日
ニュースレター 〜若い世代からのメッセージ〜 Vol.7
「若い人たちにもっと川に親しんでもらいたい」
今回は、徳島河川国道事務所の夏期実習(インターンシップ)に参加した徳島大学 理工学部 理工学科 社会基盤デザインコースの学生2名に吉野川の印象、インターンシップで学んだこと等を伺いました。
岡本 瑞季(おかもと みずき)さん(3年生)
徳島に来て初めて見た吉野川は、実家周辺の川と比べてとても大きく、海かと思っていました。大学の新入生歓迎会の後に、先輩や同期たちと吉野川の河川敷で部活や趣味などについてたくさん話し仲を深めた経験があり、今は川が身近にあることで自然を感じる時間が多くなりました。川沿いや橋の上は涼しく、景色もいいので、気持ち良く過ごせる空間であることや、構造やデザインが異なる橋が多いことも素敵だと思っています。今回の実習を通して、治水は様々な立場の人々が携わっていることを知りました。特に、流域住民の一人一人が川に対する意識や知識を高め、川と共生していくことが大切だと思いました。そのためにも、川を眺めながらゆっくりできる空間が増え、多くの人たちに川に親しんでもらうことができればいいなと感じています。
髙谷 結名(こうだに ゆいな)さん(2年生)
幼少期はよく淀川の河川敷で遊んでいて、マラソン大会やB B Q 、釣りをしたことを今でも鮮明に覚えています。吉野川での最初の思い出は、淀川と同じくらいだと思っていた川幅が予想以上に広く、自転車で橋を渡った時にどれだけ漕いでも向こう岸に辿り着かず、相当しんどかったことです(笑)。実習に参加して、川は想像以上に私たちの生活と密接に関係していることを知りました。しかし、川が普段どんな役割を果たしているのか目にすることは難しいとも感じました。吉野川のように、自然と触れ合いながら様々なアクティビティを楽しめる川が身近にある環境は素晴らしいと思うので、イベント・お祭り会場としての利用、学生たちの学校行事などでも河川敷を積極的に利用すれば、若い人たちにもっと川に親しんでもらえると思います。
Vol.8吉野川交流推進会議 会長 住友 康彦(すみとも やすひこ)さん
vol.8
世界に誇ることのできる吉野川を守り、魅力を発信し、
次の世代にしっかりとつなげていくことが私達の使命
世界に誇ることのできる吉野川を守り、魅力を発信し、
次の世代にしっかりとつなげていくことが私達の使命
 |
| 住友 康彦さん |
福永義和さんから会長のバトンを受け取り、「当会議の会長も4代目。初代会長は銀行員時代に『支店経営は駅伝競争と同じで、自分が受け取った襷をより良い状態で次のランナーに渡すことが大切』と常々話していました。歴代会長の功績を引き継ぎ、より発展させていきたい」と引き締まった表情で語る住友康彦さん(63歳)。阿波銀カード㈱取締役社長としてご多忙のなか、吉野川への思い、就任に際しての抱負等をうかがいました。
「銀行員時代は県外での勤務が長く、帰郷して吉野川を渡るたびに、その美しさと水量の豊かさに感嘆していました。また、アドプト・プログラム吉野川で、職場の人達と清掃活動に汗を流した場所でもあります」と住友さん。
幼い頃は魚獲りや堤防でのつくし採りで親しんだ吉野川。社会人になり、少年ラグビースクールのコーチとして河川敷グラウンドに通っていた頃は「吉野川が季節の移ろいの中で様々な美しい姿を見せてくれることに感動していました。夏には合宿で吉野川源流域の高知県本山町まで子ども達を引率していったこともありましたね。高知のチームと交流したり、川で泳いだり、地元の花火大会に参加したりね」と懐かしそうに語ります。気がつけばすっかり柔和な笑顔に。実は住友さんは当会議の初代会長・住友俊一さんの長男。そういえば笑った目元がそっくりです。
「おすすめの風景は、脇町潜水橋を下流側の堤防から見た景色です。幼い頃からお墓参りで穴吹町に通うたび見ていたはずですが、大人になってある時、なんと美しい風景であったのだろうと気づきました」………私達が何気なく見過ごしていたり、気づいていないものがたくさんある。吉野川もそのひとつ。「吉野川の水質・水量、そして変化に富んだ流域の景観は、世界の大河と比べてもひけをとらず、それどころか世界に誇れるものです。この郷土の川を私達の手で美しく保ち、後世につないでいくという当会議の事業に真剣に取り組んでいきたい」と熱く語ってくれました。
 |
| 社長室には、河口の代表的景観が描かれた美しい油彩画が飾られています |
 |
| 阿波銀行のアドプト区間は「うちの土手」という愛称で行員に親しまれています |
 |
夕暮れの脇町潜水橋。山田洋次監督の映画『虹をつかむ男』でも描かれた美しい風景 |
2024年12月7日土曜日
まるごと吉野川魅力再発見講座(2024年12月21日)開催案内
 |
チラシPDF
<参加者募集は終了しました>
「恵みの宝庫“吉野川”創造プロジェクト」の一環として、吉野川との関わりによって育まれてきた歴史・文化・環境をテーマに、吉野川の魅力をお伝えする「まるごと吉野川魅力再発見講座」を開催します。
◎開催日
令和6年12月21日(土)12:15~17:30
◎内容
吉野川流域の伝統産業工業等を巡る~四国三郎・吉野川下流域バスツアー~
◎対象・定員
20名程度(申込多数の場合は抽選)
(小学生以下は保護者同伴)
◎参加費 無料
◎申込〆切
令和6年12月16日(月)17時必着
◎申込方法
添付の「チラシ」の申込書または必要事項を記入し、次のいずれかの方法でお申し込みください。
1.メール kasenseisakuka@pref.tokushima.lg.jp
2.郵送 〒770-8570徳島市万代町1丁目1番地
徳島県庁 河川政策課 宛
※詳細はチラシでご覧ください。
2024年9月25日水曜日
「利根川流域フォーラムinみなかみ町」(令和6年10月18日・19日)開催案内
登録:
コメント
(
Atom
)